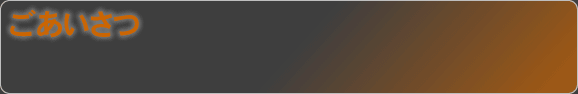|
|
新しい伝統の芽生え
第3回山本鼎版画大賞展実行委員長 小宮山 量平
わが《山本鼎版画大賞展》は、その第1回から第2回へ、更に第3回へと、量においても質においても、右肩上がりの発展を示し、今やわが国で最も注目されるトリエンナーレと評価されるに至っております。とりわけ本年の第3回展に至って、その眼で見れば、正に山本鼎の名を冠するにふさわしい独自性が、くっきりと見えてきたとさえ言えるのではないでしょうか。それというのも、第1回展以来ほとんど変わることなく審査の労をとられて、視野も広く温かいチームワークを実現してこられた審査員諸氏による“指導性”はもちろんのこと、それと阿吽(あうん)の呼吸でひびき合う応募者のみなさんが示された“創造性”の高まりとが、いつしか固い結びつきを示し始めたからなのでしょう。
かえりみれば、ほかならない信州上田の地に山本鼎の名が定着するに至ったについては、格別の因縁があるのです。わが国の近代的文化・芸術への開眼が、明治時代における西欧文化の“総論的な”摂取を主流とした時期から、大正時代における“各論的な”定着性探求の時期へと巨きくうねり始めたころに、山本鼎は留学から帰朝したのでした。すでに澎湃として反アカデミズムの狼煙(のろし)をかかげていた西欧画壇で《自由画》への火種を胸底に宿した彼が、とりわけ帰路に接したロシアの農民美術としての版画に着目するに及んで、そうした民衆的芸術の受け皿となりうる土地こそが、彼の還るべき“ふるさと”と考えられたのでしょう。
折から大正デモクラシーの開花期を迎え、その児童文化面での温床となった《赤い鳥》の誕生も、広く青年層の文学・美術への開眼を促した《白樺》の創刊も、更には当時の学問的啓蒙の先駆的青年運動となった《上田自由大学》の発足も、すべては、正に“日本のヘソ”とでもいうべきこの上田の盆地に旺んな気運をもたらしておりました。まぎれもなくこの地こそは、山本鼎によって選ばれるべき絶好の受け皿であると同時に、山本鼎その人の思想と行動を更に一層守り育てる革新的な歳月を重ねて参りました。そんな人物と土地柄との深い結びつきこそが、半世紀を経た今日、これほどの《大賞展》という大輪の花を開花せしめるに至ったことを、改めてかえりみないではいられません。
それにつけても、日本の近代史が如実に物語っているように、このような芸術創造のための“ふるさと”が守りぬかれ、一層の発展が約束されるためには、何よりもおおらかで自由な精神の羽ばたきが望まれるはずです。このトリエンナーレが、21世紀的な芸術創造の前衛性を目ざして、新鮮で伸びやかな試行の土壌へと開拓されつつあるーそんな予感がするのです。回を重ねるにつれて、そうした新しい伝統が築かれるに違いない、と、期待して己みません。